 |
| 住宅と電線の間 |
依頼が来るのはいつも、こんなケースです。
1)電線や家が目の前
2)電線よりはるかに高い木(15m以上)
3)庭がせまい
4)道路が目の前
5)クレーンや高所作業車が使えない。
こんな場合は、是非おまかせ下さい。
ロープのみで安全確保し、上から少しずつ切り落とします。
|
|
 |
| テクニック総動員 |
電線・外灯・建物・あらゆる障害物を避けながら、正確に方向を決めながら少しずつカット。春〜秋は成長期なので、水分が多く生木の比重はデータブックどおりではありません。体積から重さを注意して計算し、細かくカット・・・根元の直径50cm・総重量は、推定1トン以上の松・・・・・
上り方もいろいろです。
まずは、枝にロープをかけてそのままロープクライミング。
後は、木に直接専用のロープを巻きつける、尺取虫方式で少しずつ上ります。あぶみも使います。
また、調節型ランヤードで木と体の距離を固定。
安全第一です。とにかく、全てのテクニックを使います。
|
|
 |
| 登り方あれこれ |
まず、スリングショット(競技用のパチンコ)で紐をできるだけ上方のしっかりした枝に引っ掛けます。うまくいったら、ロープを引き上げセットします。
|
|
 |
最初の枝まで通常の手動ロープ登高器を使いシングルロープで登ってから、さらに上を目指します。最初の位置で既に10mは超えています。
ここからは、2本のロープを幹に巻き付けコツコツ登る「巻き登り」(勝手に命名)で登ります。
小枝も手のこで、丁寧に払いながら登ります。
幹を切った時に、枝で怪我をする事が最も多いので、これは絶対かかせません。
|
|
 |
|
|
倒す側(オーバーハング側)に方向を決める、受け口のVカット。これが全てを決めるので、チョークでマークしてから、正確にカットします。
カットがうまくいったら、背側から切り込む。(追い口)
下方の安全を確認したら、一気に・・・
ナイスショット!! 見事な・・・・写真の腕前?
|
|
 |
| 植木屋さんが・・・・ |
神戸の街中では、まずお目にかかれない光景なので、ギャラリーがいっぱい集まってきました。
道路の反対側からは、植木屋さんがじっとみているので、ミスはできない。正直言って大緊張・・・・・・。
→ → →→ → →
予定通り、大成功!!!
|
|
 |
特に樹上では、体勢が悪くどうしても、思い通りの姿勢がとれない事がありますが、Vカットはきっちりと!!
根元でカットする場合の受け口は、通常上側を斜めにカットしますが、樹上の中間でカットする場合は、下側を斜めにカットします。この方法にすると、倒れる時に裏側にすべってこないので作業員の安全が確実に確保できるからです。
チェーンソーの危険性を熟知し、操作に熟練した者だけに許される作業といえます。何重にも安全対策をほどこし、緊急事態にそなえてから作業をします。
安全作業に不安がある場合は、手のこでコツコツ進めます。 |
|
 |
ロープを使う木の上り方は、ツリークライミング技術として世界的に広く普及しています。カナダのアーボリスト(林業従事者)が使っていた木登りテクニックとケービング(洞窟探検)で利用していたテクニックが融合したような大変合理的で安全な登り方です。
弊社も基本的なテクニックを組み合わせ、独自の方法を開発して登っています。樹上で長時間安定した作業ができるように、いろいろ工夫をしています。
仕事を離れて、木に登って森の中で遊ぶ楽しさは、また格別です。木登り専用の道具も数多く販売されていますし、日本古来からある(ぶり縄)や自分で工夫した方法を駆使して登るのもまた、楽しいものです。
|
|
 |
真っ直ぐにのびる針葉樹の中でも、杉の枝は折れやすく細いので、枝にロープをかけて登る訳にはいきません。
2本のロープを幹に巻き付け、尺取虫のように登ります。
2本のロープを巻きつける基本的な考え方は、日本古来の「ぶり縄」と同じですが、登り方はかなり異なります。
ロープアクセスで使用する道具の長さを少し変えてセットし、下側のロープクランプには自作の2段アブミや、市販のアブミをセットします。
これに調節型ランヤード(体を木に固定するロープ)があれば完璧です。木や電柱・鉄塔作業では必須アイテムです。
アッセッションやSTOPで幹との距離をうまく調節しながら登ると早く登れます。チェーンソーなどで作業する場合は、自作のアルミアブミのほうがガッチリしていて疲れません。
とにかく自分に合った方法を工夫する事が大切です。
樹種や幹の太さでも登る方法は少しずつ違います。
|
|
 |
| 巻き登り開始 |
下側の巻きロープに付けた「あぶみ」がポイントです。
2段あれば十分です。
2段上がって、とりあえず調節型ランヤードで体を固定。
上の巻きロープをさらに上へセットし、ぶら下がる。
調節型ランヤードと下の巻きロープを緩め、下の巻きロープを少し上へずらします。この繰り返し。
説明はややこしいけど、やってみれば簡単。
|
|
 |
| 調節型ランヤード |
調節型ランヤードをセットすると、ハーネスが背もたれ椅子のようになって、腰をホールドしてくれます。
ハーネスの左右の位置にフックがあり、片方から木に回してもう一方へフックします。長さが調整できる器具がついているので、丁度良い位置で止めることができます。
電工用安全ベルトにもこのようなタイプがありますが、ここで使用しているのは、ペツル社のグリヨン+ランヤード。
樹木の保護とロープの保護・滑り止めを兼用して、農業用ホースにランヤードを通す場合もあります。
アブミは、ホームセンターのアルミ角パイプで自作しています。幅広なので、両足が置けるし、足もいたくなりません。地上でふつうに立っている感じです。
いろんな道具や方法がありますが、自分に合った方法を工夫する事が大切です。やっぱり安全第一です。
下り用のロープと下降器も忘れずに!
|
|
 |
| 下りはロープで一気に! |
降りるときは、ロープに下降器をセットして一気に降ります。
2度目に登る時は、シングルロープで登れるので簡単です。 |
|
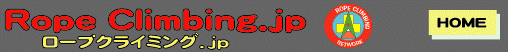 |

